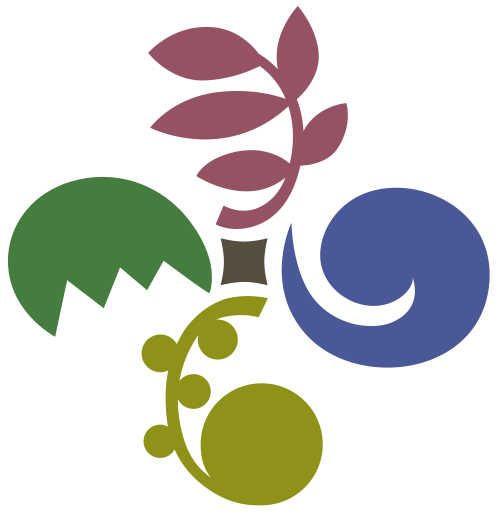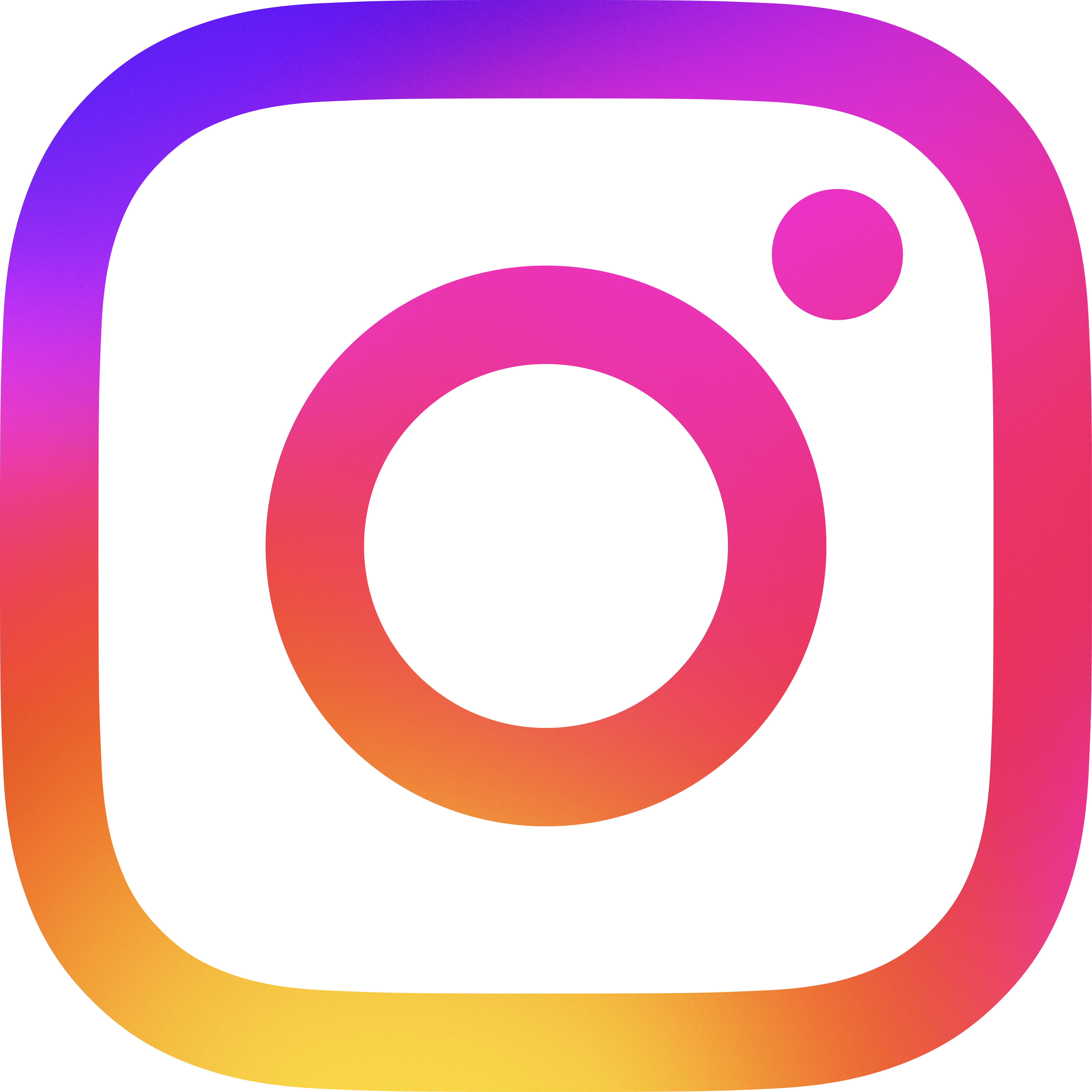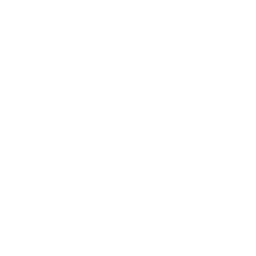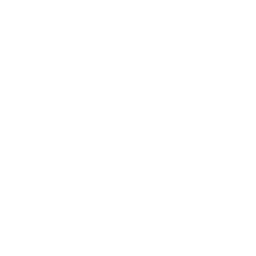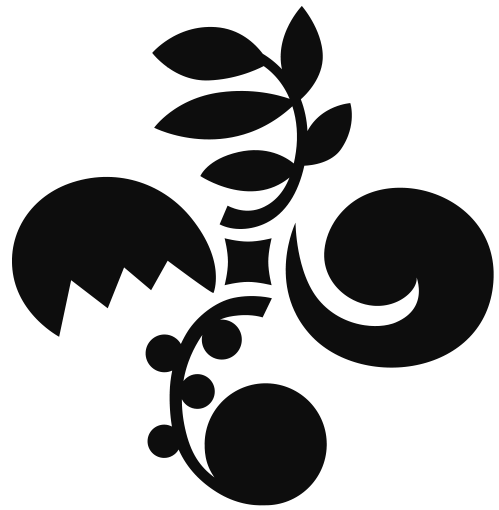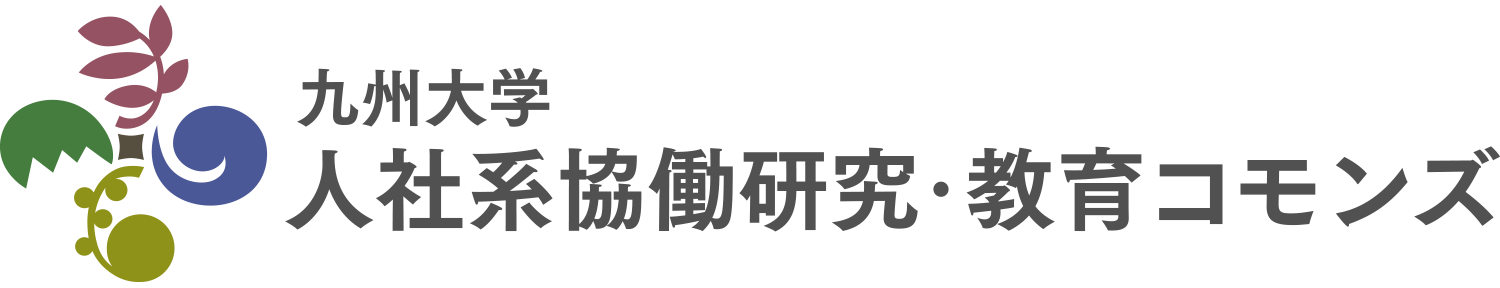おしらせ Information
九州大学人社系協働研究コモンズ
Collaborative Platform in Research and Education
on Humanities and Social Sciences

研究コモンズの4つの指針はこちら
Event News!
10月3日 開催
第34弾 企画
知の形成史 #15
を開催します。
2025.09.16

▶ 柳愛林(九州大学法学研究院准教授 政治学部門)
カレーライスと政治思想――日本近代における西洋政治思想の受容
人類が群れをなして生活を始めた瞬間から
▶ 工藤孔梨子(九州大学病院アジア遠隔医療開発センター講師)
▶ 司会:木下寛子(九州大学人間環境学研究院准教授)